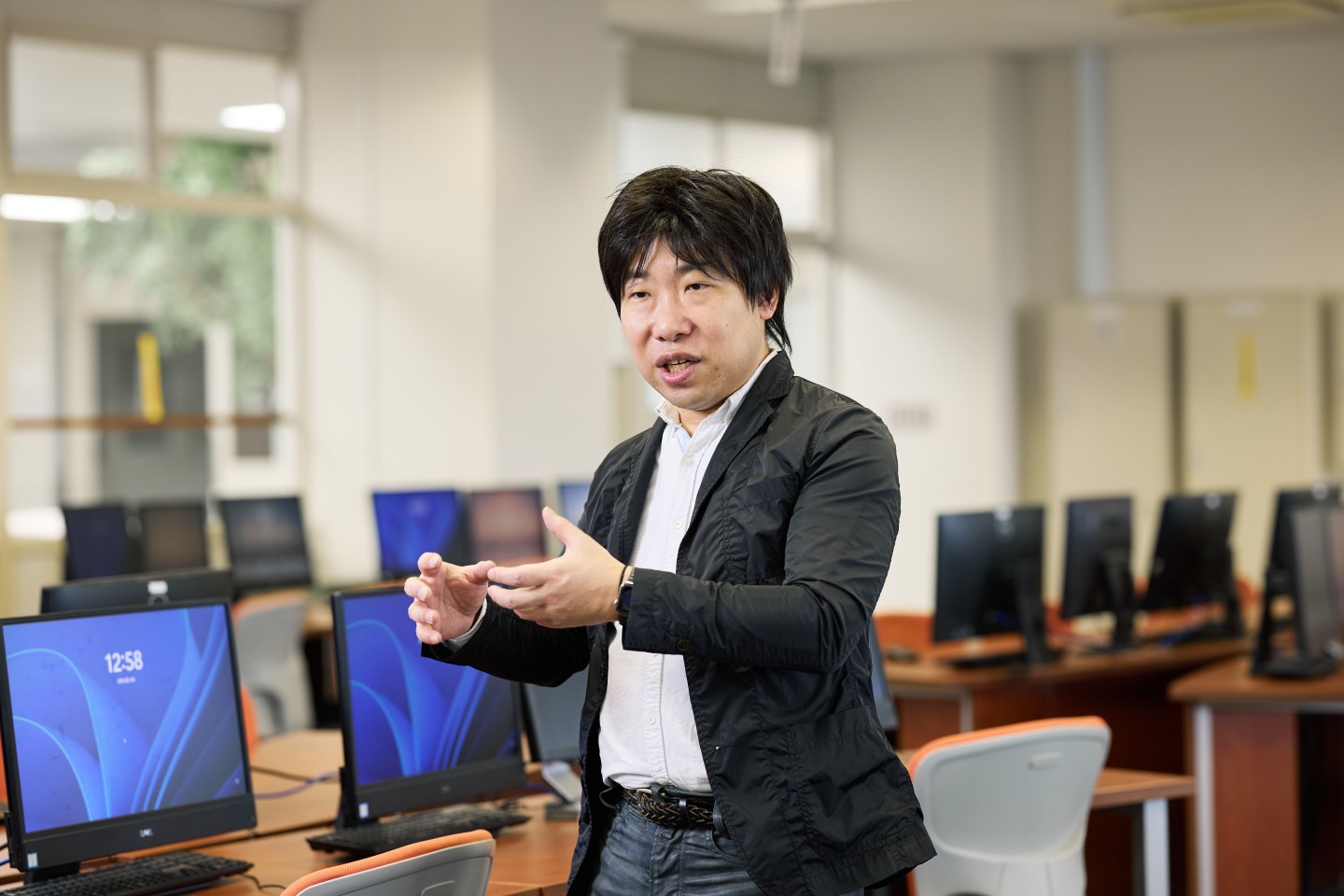<演奏特徴分析>
本研究では西洋音楽の鍵盤楽器演奏を主な対象として、特定の演奏者が持つ暗黙知に寄与する要因を一般的な情報の組合せに基づく形式知として体系的に説明する手法を提案しています。 演奏者は楽譜の指示から楽曲の意図を解釈し、楽器の操作に相応しい表情を付与しています。 同一の楽曲では指示内容も共通ですが、指示をどう解釈して楽器の操作に反映するかは演奏者の暗黙知に依存するため、実際の演奏に付与される表情は演奏者ごとに異なります。 特定の個人がどのような条件でどのような行動をするのかを自然言語などに依存しない一般的な情報に基づいて記述できれば、個人に固有の特徴と、それに寄与する要因を、客観的に説明できるようになります。
本研究ではさらに、演奏者の楽曲解釈に寄与した要因を客観的に説明し、演奏間の表情の類似性を比較する用途への応用も実施しました。特定の人間の経験や勘などに依存せず、特定の自然言語を使用することによる表現の偏りにも左右されないことを特徴としています。演奏の指示と実際に付与された表情との因果関係を、データのみから分析することが可能なツールを提案する取り組みです。評価実験からは、演奏間の表情の類似性についての人間の主観に準じる分析結果を、客観的な指標を伴って自動的に獲得可能であることが示されています。
<自動演奏表情付け>
とくに鍵盤楽器演奏においては、上記の研究で得られた技術をもとにした応用研究を実施しています。 その一例には、任意の楽譜から人間らしい表情を付与した演奏を生成する「自動演奏表情付け」タスクがあります。
既存の類似研究の多くでは演奏の生成過程でシステムを実行する人間の意図が入り込む設計となっていますが、本研究で提案したシステムはそうした恣意性を徹底して排除することを設計思想としています。表情づけに使用する元の演奏者が残した特徴をそのまま反映しつつ、未知の楽曲の演奏でも最も高い確率で自然性を保つような最適な表情を自動的に付与できることに特徴があります。評価実験からは、元の演奏が備える表情の品質を多様な楽曲において反映できることや、特定の演奏者が持つ表情の特徴を再現した演奏を生成可能であることが示されています。また、本研究の過程で実装されたデモシステムは、2013年に開催された国際的な自動演奏生成システムによるピアノ演奏コンテストの自律演奏システム部門に出場し、優勝の評価を獲得しています。
<演奏技能教育支援>
上記の研究で得られた経験をもとに、近年では楽器の種類に制約されないセンシング手法の開発を進めています。 そのほか、社会的により多くの人にとっての楽器演奏体験の向上に資するための応用範囲を拡げており、研究としての発展性を充実させる取り組みを進めています。